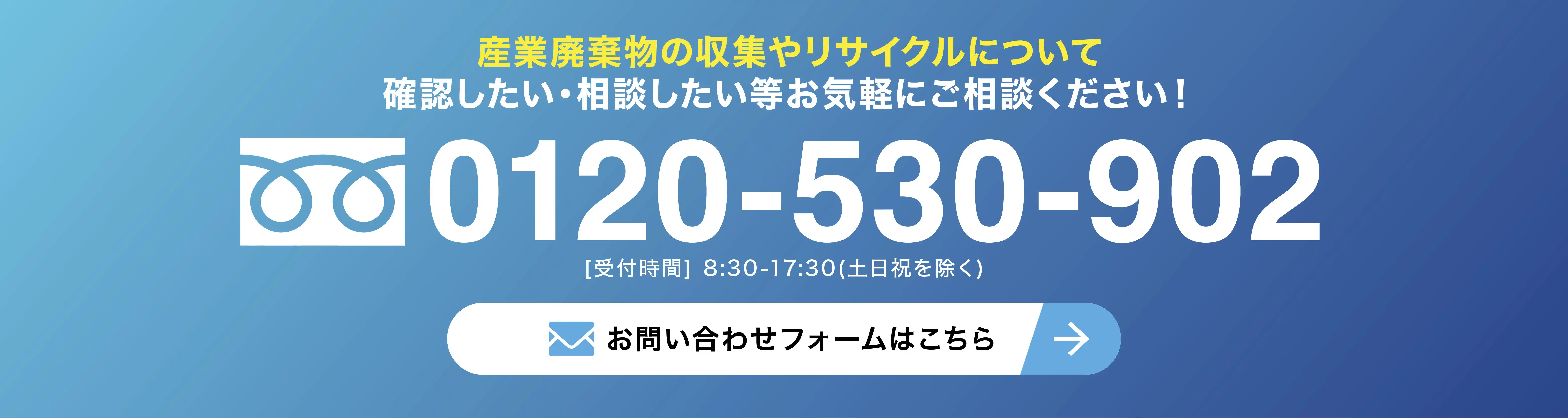目次
海洋プラスチック問題の現状と社会的リスク
海洋プラスチックとは、海岸や海中に漂うプラスチックごみのことを指します。海洋プラスチックは、海洋ごみ全体のその6〜7割をプラスチックごみが占めているとされています。
海の生態系を破壊することはもちろん、食卓にのぼる魚介類を通じて私たちの健康にも関わる「海洋プラスチック問題」は、いまや全人類に関わる課題といえるでしょう。
ここでは、海洋プラスチック問題の現状と、それらが及ぼす生態系・人間への影響について解説します。
世界の海に流出し続けるプラスチックごみ
海に流出するプラスチックごみは、毎年約800万トンにものぼると推計されています。この大半は、ポイ捨てや不適切な廃棄物管理により、陸から川を伝って海へと流れ出たものです。
また、海上輸送中の船舶からの流出も問題となっています。例えば、2021年5月には、プラスチック製品の原料であるペレットが海に大量流出する事故が発生し、国際的に包装や積載方法の見直しが求められました。
陸上からの流出も、海上輸送の事故も、完全に防ぐことは困難です。海洋プラスチック問題は、さまざまな原因が多面的に関係しており、一つの原因を解決するだけでは対処できません。
海洋プラスチックが及ぼす生態系・人間への影響
海洋プラスチックは、海の生き物に深刻な被害を与えています。生き物に誤って飲み込まれたプラスチックは消化されず体内に蓄積されます。これが、内臓を傷つけたり、腸閉塞を引き起こしたりして、命を落とす原因となっているのです。
2019年には、100kg以上のプラスチックごみを飲み込んだクジラの死体がスコットランドで発見されました。ノルウェーやタイでも同様の事例が報告されています。
また、海洋プラスチックは、人間の健康への影響も懸念されています。魚介類を通じて私たちの身体に取り込まれるマイクロプラスチックが、人体にどのような影響を及ぼすかは、現時点では正確に判明していません。しかし、免疫機能の低下やホルモン異常、発がんリスクなどの長期的な健康リスクを引き起こす可能性も示唆されており、見過ごせない問題であることは間違いないでしょう。
なぜ海洋プラスチックごみの回収・再利用は難しいのか

海洋プラスチックは、以下の理由から、一度拡散してしまうと回収や再利用が困難です。
-
・海水による塩分汚染や異物混入の課題
-
・物理的な回収の困難さ
-
・従来処理の限界と環境負荷
それぞれ見ていきましょう。
海水による塩分汚染や異物混入の課題
プラスチックごみは、海水に長期間さらされると、塩分や不純物を多く含むようになります。こうなったプラスチックは通常の処理施設でのリサイクルが難しく、やむを得ず焼却処理に回されることが少なくありません。
また、プラスチックは塩分や塩素を含むため、燃焼時にダイオキシンなどの有害ガスを発生させたり、焼却炉の寿命を著しく縮めたりするリスクがあります。そのため、高度な処理設備を持つ一部の施設でしか対応できず、コストや処理能力に限界があります。
物理的な回収の困難さ
海洋に流出したプラスチックごみは、紫外線や波の影響で劣化・細分化され、マイクロプラスチックとなって広範囲に拡散します。特に、5mm以下のマイクロプラスチックは肉眼での識別が難しく、海中からの回収は極めて困難です。
さらに、広い海域に点在するごみを集めるには膨大な労力とコストがかかります。そのため、現実的な回収率は極めて低いです。だからこそ、初めからごみを出さない取り組みが、より重要とされています。
従来処理の限界と環境負荷
通常、プラスチックごみを処理する際は、以下の3種類の方法を用いることで、環境への負荷を減らすことが可能です。
-
・マテリアルリサイクル:原料として再び製品化する
-
・ケミカルリサイクル:化学工業原料などに分解・再利用する
-
・サーマルリサイクル:熱エネルギーとして利用する
しかし、前述の通り、海水の塩分にさらされた海洋プラスチックは、これらの方法でのリサイクルが困難です。海洋プラスチックを再資源化するには、塩分除去や異物選別といった前処理技術の開発と、対応体制の整備が欠かせません。
社会全体で取り組むべき課題と企業の役割
海洋プラスチック問題は、一企業や自治体だけでは解決できない、複雑かつ広範な環境課題です。そのため、流出を防ぐ仕組みづくりと、企業による主体的な取り組みを軸に、多様な関係者との連携が欠かせません。
ここでは、ごみの流出を防ぐ仕組みづくりや企業が取るべき行動、連携の必要性について解説します。
ごみの流出を防ぐ仕組みづくり
海洋プラスチックごみの多くは、陸上から川を経て海に流出しています。ごみが流れ出る原因は、ポイ捨てや風で飛ばされただけではありません。事業に伴って生じた廃棄物の不適切管理も一因です。そのため、事業者も含め、排出源となる場所での対策が不可欠となります。
日常生活や事業活動における、ごみの発生を減らすための考え方として、「Reduce(リデュース)」「Reuse(リユース)」「Recycle(リサイクル)」から成る「3R」を紹介します。
| 具体的な行動例(事業活動) | 具体的な行動例(個人) | |
|---|---|---|
| Reduce(リデュース) ごみになるものを減らす | 過剰包装を見直し製造工程での端材・廃材の発生を抑える | マイバッグやマイボトルを使ってレジ袋やペットボトルの使用を減らす |
| Reuse(リユース) 繰り返し使う | 梱包資材や備品・什器を社内で再利用する | 詰め替え容器を活用して製品を繰り返し使う |
| Recycle(リサイクル) 原材料として再利用する | 廃棄物の分別を徹底し、リサイクル業者と連携して再資源化する | プラスチックごみを分別し、リサイクルに回す |
企業に求められる姿勢と行動
企業には、製品の設計から廃棄・流通・輸送に至るまで、あらゆる工程で環境負荷を抑える、責任ある姿勢が求められています。こうした考え方は「EPR(拡大生産者責任)」として国際的にも重視されています。単なる製品開発にとどまらず、ライフサイクル全体を見据えた対応が必要です。
例えば、製造業や流通業では、包装資材の削減や分別しやすい素材の選定、適切な廃棄処理の体制整備が欠かせません。また、船舶や海運に関わる事業者であれば、積載方法や管理体制の見直し、漂流物の回収体制づくりなどが具体策として挙げられます。
こうした取り組みは、企業ブランドの向上だけでなく、顧客や自治体、パートナー企業との信頼醸成にも寄与するでしょう。社会課題の解決に貢献する姿勢は、今や企業価値を左右する重要な要素となっています。
多様な主体が連携する必要性
海洋プラスチックごみの削減には、国・行政・企業・市民といった多様な主体の連携が不可欠です。行政は方針を示し、補助金や助成制度を通じて対策を後押しします。企業は脱プラスチック製品の開発や新しい回収システムの構築に取り組むことが期待され、市民は日常生活の中でごみを減らす意識と行動が求められるでしょう。
このように、各主体が協力し合うことで、大規模で継続的な改善が実現します。海洋ごみ問題は、企業や行政の努力だけでは解決し得ない「全員参加型」の課題であると認識しましょう。
海洋ごみ削減に向けた地域連携の取り組み(当社事例)
海洋プラスチック問題の解決には、地域社会との協働が欠かせません。当社では、廃棄物処理業者としての専門性を生かし、地域住民や行政、教育機関と連携した環境保全活動を継続的に実施しています。
ここでは、環境のミカタが実際に取り組んでいる海岸清掃活動の事例を紹介します。
ウミガメの産卵地を守る海岸清掃活動
毎年、御前崎中学校が主催する「亀バックホーム大作戦」に参加しています。この活動は、ウミガメの産卵地である御前崎海岸を清掃することで、生態系を守ることを目的とした地域連携イベントです。
静岡県産業廃棄物処理協同組合の一員として、当社も海岸美化に貢献しています。中学生や地域住民、ウミガメ監視員、市役所職員とともに活動することで、次世代を担う子どもたちに環境保全の意識を育む機会にもなっているのです。

流域クリーン大作戦など他地域での活動
御前崎海岸以外にも、静岡県内のさまざまな地域で海岸・河川清掃活動に参加しています。例えば、「やいづビーチクリーン大作戦」や、静岡県が推進する「6R県民運動※」の一環で行われる清掃イベントです。駿河湾沿岸や富士・焼津地域の海岸において、市民や企業が協力しながらごみを回収しています。
特に、焼津市で行われた清掃活動では、約2,000人の参加者とともに7.5トンものごみが集められ、大きな成果を挙げました。今後も当社は、地域住民や行政、教育機関と連携しながら、身近な行動から持続可能な未来を築くための活動を続けていきます。
※6R運動:リデュース・リユース・リサイクルに加え、Refuse(断る)・Repair(修理)・Return(自然に返す)といった行動を含めた静岡県独自のごみ削減運動。

まとめ
海洋プラスチックごみ問題は、地球規模で広がる環境課題であり、私たち一人ひとりの暮らしと密接に関わっています。年間800万トンという膨大な量のプラスチックが海に流出し続ける現状は、もはや看過できるものではありません。企業としても、製品の設計やごみの発生抑制にとどまらず、地域との連携を通じたさらなる環境保全活動が求められます。
当社は今後も、循環型社会の実現に向けて、地域社会とともにできることから行動を続けていきます。一人ひとりの意識と行動の変化が、海洋環境の保全と持続可能な未来の実現につながることを信じています。