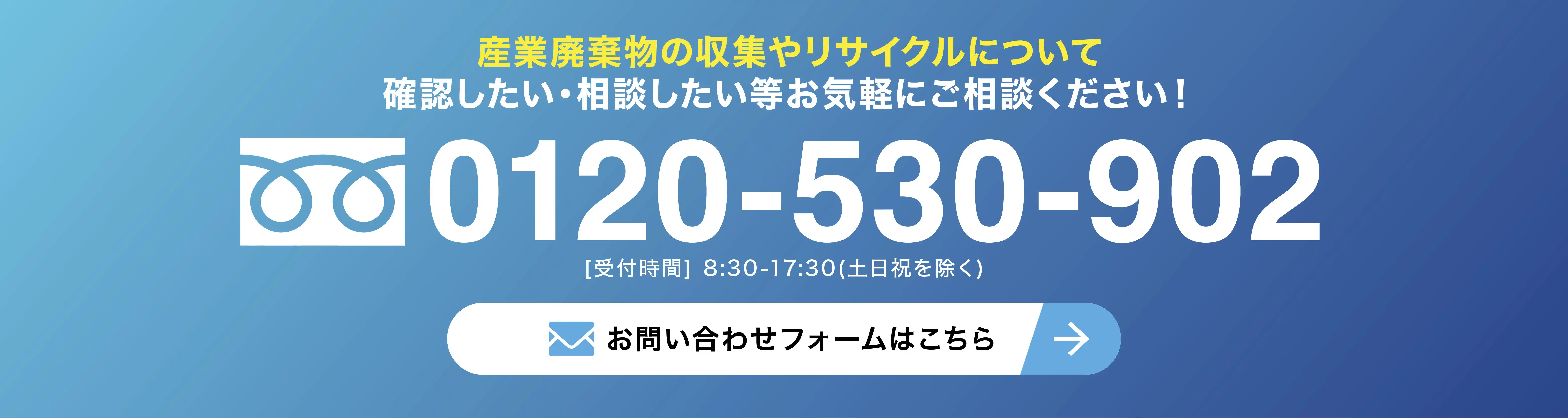リチウムイオン電池は、繰り返し充電して使える高性能な電池です。小型で大容量という特長を持ち、スマートフォンやパソコンなど、多くの機器に活用されています。
このように利便性の高いリチウムイオン電池ですが、廃棄方法を誤ると火災などの重大事故につながります。
この記事では、リチウムイオン電池の廃棄が注目される理由や、火災事故の実例、事業者として適正に処理するためのポイントについて解説します。
目次
リチウムイオン電池の廃棄が注目される理由
リチウムイオン電池は、小型かつ高性能なため、以下のようなさまざまな製品に使用されています。
-
・スマートフォン
-
・パソコン
-
・モバイルバッテリー
-
・加熱式たばこ
-
・ハンディファン
-
・充電式カイロ など
リチウムイオン電池は、一般家庭からだけでなく、事業活動に伴って発生する廃棄物としても多く排出されます。
しかし、リチウムイオン電池は、外的な衝撃や圧力が加わると発熱・発火の危険があるため、適切に廃棄することが非常に重要です。実際に、リチウムイオン電池を他のごみとまぜて廃棄したことで火災が発生する事故が全国で多発しており、環境省からも、正しい廃棄方法を守るよう通達が出されています。
近年では加熱式たばこや電子カイロなど、「リチウムイオン電池が入っていると気づきにくい製品」も増えてきました。これらの製品を、リチウムイオン電池の内臓に気づかず可燃ゴミとして廃棄してしまうケースも少なくありません。製品を廃棄する際には、リチウムイオン電池が使われていないかを確認することが重要です。
誤った廃棄による火災リスクと実例
ここでは「リチウムイオン電池の危険性」と「実際の火災事例」について見ていきましょう。
なぜリチウムイオン電池は危険なのか
リチウムイオン電池は、+極と-極の電極が交互に折りたたまれた構造になっています。-極はセパレーター(絶縁膜)によって+極と直接接触しないよう保護されているため、通常の使用においては発火の心配はありません。
しかし、外部から強い圧力が加わりセパレーターが破損すると、電極同士が接触してショートが発生します。ショートによって大量の電流が流れ、高温になります。
さらに+極の材料に使用されている金属酸化物が酸素を放出するため、発火の危険性が非常に高いです。
混入による火災事故の発生事例
リチウムイオン電池が原因となる火災事故は、令和5年度に全国で8,543件発生しています。なかでも、モバイルバッテリーによる発火が最も多く、次いでスマートフォン、電動アシスト付自転車などが原因となるケースが多いです。
出典:市町村におけるリチウム蓄電池等の適正処理に関する方針と対策について

発火した後のリチウムイオン電池
以下に、実際に発生した火災事故の事例を紹介します。
-
【事例①】
-
事務所で、携帯型扇風機を充電したまま外出したら携帯型扇風機から出火。下階の居住者が火災報知機の音で火事に気付き消防へ通報、事務所は全焼した。
-
【事例②】
-
プラスチックごみや不燃ごみにモバイルバッテリーを内蔵した廃棄物が紛れ込み、ごみ収集車内で押しつぶされ発火。ごみを入れる積載スペースが全焼し消防により1時間半後に消火された。
-
なお、出火したごみ収集車は一般家庭からではなく、事業者からのごみを回収していた。
-
【事例③】
-
廃棄物処理施設で、可燃ごみの破砕処理中に発火。リチウムイオン電池を含む機器が混在しており、破砕機の圧力で発火したとみられる。
-
2024年4月に、環境のミカタでも同様の火災が発生。幸いにも人的被害はなかったものの、アースプロテクションセンター第二工場が全焼した。


排出事業者が適正に処理するためのポイント
リチウムイオン電池の廃棄にあたっては、正しい知識と処理手順を理解しておかないと、火災リスクだけでなく法令違反にもつながります。
ここでは排出事業者として適正に処理を行うための重要なポイントを解説します。
対象となる廃棄物を知る
リチウムイオン電池は、ノートPCやスマートフォン、モバイルバッテリー、電子工具、電子たばこ、ハンディファンなど、さまざまな機器に使用されています。一見すると電池が入っているとは気づかない製品も少なくありません。リチウムイオン電池を明確に識別できるよう、社内掲示物や注意書きでの周知を行いましょう。
また、事業として使用したものでなくても、従業員が私物として持ち込んだ製品などからリチウムイオン電池が混入するケースもあります。他のごみと混ざって廃棄されないよう、社内での注意喚起を徹底してください。
適切に保管・分別する
リチウムイオン電池は、廃棄するまでの保管方法にも十分な配慮が必要です。下表は、電池の状態別の保管方法をまとめたものです。
| 電池の状態 | 保管方法 |
| 膨張・変形した電池 | 膨張変形した電池は発熱・発火の恐れがあるため、耐火性の容器に保管し、延焼しない場所に保管する。 |
| 製品から取り外せない電池 | 製品から取り外せない電池は無理やり取り外す際に変形する恐れがあるため、そのまま保管する。 |
| 異なる種類の電池 | 電池の種類ごとに保管する入れ物を変える。 |
いずれのケースでも、保管場所は高温多湿や直射日光を避け、水に濡れない場所を選びましょう。また電池の端子同士が接触してショートしないよう、セロハンテープやビニールテープで絶縁処理をしてから保管することが大切です。
適切に廃棄する
処理対応が可能な許可業者に委託する
事業活動で使用されたリチウムイオン電池は、自治体の回収対象ではありません。産業廃棄物として適切に処理するためには、対象品目の許可を有し、実際に処理体制を備えている業者に委託する必要があります。
単に許可を持っているだけではなく、処理施設の有無や対象品目への対応可否を事前に確認することが重要です。無許可の業者や、処理体制のない業者に委託した場合、廃棄物処理法違反に問われるリスクがあります。
委託先の選定にあたっては、次の2点を必ず確認しましょう。
-
・産業廃棄物収集運搬業の許可を自治体から得ているか
-
・対象品目に該当する産業廃棄物処分業の許可を有し、かつ処理に対応できる工場や施設が整っているか
また、処理委託時にはマニフェスト(産業廃棄物管理票)が発行されるかどうかも確認しましょう。マニフェストは、排出事業者が5年間の保管義務を負う重要な書類です。
JBRCに回収依頼する
JBRC(一般社団法人JBRC)は、電池・電機メーカー等が出資するリサイクル団体で、使用済み充電式電池の回収・再資源化を全国規模で推進しています。JBRCの回収スキームは、一般家庭の排出者に加え、事業者も対象としており、回収対象製品であれば誰でも利用可能です。
事業者が継続的に廃棄電池を排出する場合は、JBRCの「回収拠点」に登録することで、専用容器や回収票の提供を受け、法令に準拠した処理が効率的に行えます。特に、自社で産業廃棄物処理体制を構築することが難しい小規模事業者にとって、有効な選択肢となります。
詳細な登録手続きや対象製品については、JBRC公式サイトをご確認ください。
回収後のリチウムイオン電池はどう処理される?
回収されたリチウムイオン電池は、火災リスクを伴う可燃性廃棄物である一方、再資源化が可能な有用資源でもあります。適切に分別・回収された電池は、真空加熱炉などで高温処理され、可燃性の有機成分を除去したのち、金属や構成材料ごとに分類される工程へと進みます。
続いて、酸溶解や高温溶融などの手法を用いて、コバルト、ニッケル、銅、鉄、アルミニウムなどの有価金属を回収。これらの金属は、新たな電池や金属製品の原材料として再利用され、資源循環に役立てられています。
一方で、リチウムは経済的な理由から再資源化が難しく、多くの場合スラグ化処理を経て、道路舗装材などに利用されるのが一般的です。
このように、リチウムイオン電池は「廃棄物」ではなく「資源」として向き合うことが求められます。事業者にとっても、適正処理と再資源化の両立は、環境への配慮と企業価値の向上を両立させる重要な取り組みといえるでしょう。
まとめ
リチウムイオン電池は、小型で高性能な電源として多くの場面で活用されていますが、誤った扱いや廃棄方法によって発火・爆発などの重大な事故を招く可能性があります。
適切に分別・廃棄を行うことは、処理業者の安全確保や環境保全の観点からも極めて重要です。事業者としては、社内ルールの整備や従業員への継続的な啓発を通じて、誤廃棄のリスクを未然に防ぐ体制づくりが求められます。
廃棄物の回収や処理方法についてご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。