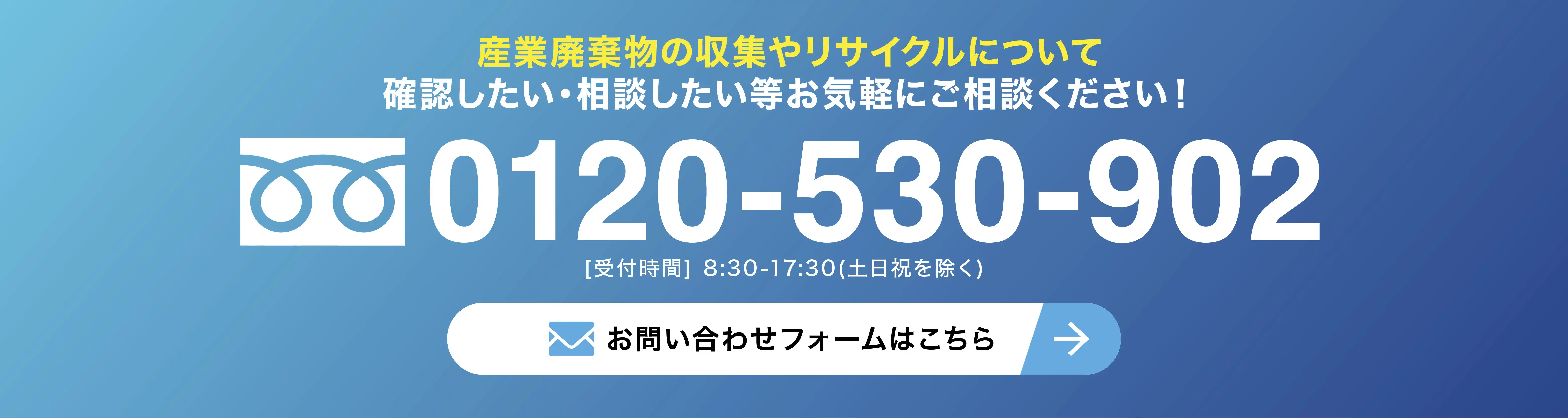産業廃棄物の不法投棄は、1970年代から社会問題として取り上げられてきました。監視体制や規制が強化され、厳しい罰則が設けられた現在でも、全国で毎年100件以上、合計4万トンを超える不法投棄が確認されています。
本記事では、不法投棄の実態や背景、実際に起きた事例、企業が直面するリスクと防止策について解説します。
産業廃棄物の正しい処理のために、ぜひ最後まで記事を読んでみてください。
目次
産業廃棄物の不法投棄の実態
産業廃棄物の不法投棄には厳しい罰則が設けられており、違反した企業は社会的な立場を失いかねません。にもかかわらず、なぜ不法投棄はなくならないのでしょうか。
ここでは、不法投棄が多い場所や背景、投棄されやすい廃棄物の種類、不法投棄による見えにくい影響について解説します。
不法投棄が多い場所と背景
不法投棄は、人目につきにくく監視が行き届きにくい場所で発生しやすい傾向があります。
代表的なのは、山林、河川敷、空き地、港湾などです。そのため、発覚が遅れやすく、撤去までに時間を要するケースは少なくありません。
その背景には、産業廃棄物の処理費用を回避したい事業者や、不正を働く処理業者の存在が挙げられます。委託業者だけでなく、排出事業者の従業員や下請け現場による不正投棄が起こる場合もあるのが実情です。
不法投棄のピークは平成10年代でしたが、令和に入ってもなお年間100件以上、総量で4万トンを超える不法投棄が続いています。現在減少傾向にはあるものの、完全に解決には至っていません。
不法投棄されやすい廃棄物の種類
不法投棄されやすい廃棄物は、処理費用が高額なものや、分別・処理に手間がかかるものです。代表的なものは以下のとおりです。
-
・建設廃材(コンクリートがら、木くず、石膏ボードなど)
-
・廃タイヤや家電リサイクル対象製品
-
・汚泥、廃油、廃プラスチック類
-
・医療廃棄物(感染リスクがあり特に危険)
なかでも、がれき・汚泥・木くずといった建設系廃棄物は、不法投棄の件数が圧倒的に多いです。コンクリートがら(がれき類)の処分費用は、高くなる場合もあるため、コスト削減を目的として不法投棄されることが多くなっています。
不法投棄による見えない影響
不法投棄の問題は、「景観を損なう」だけではありません。実際には、環境・経済・社会の面で大きな負担を与えます。
-
・環境:土壌や地下水の汚染、有害物質による生態系の破壊
-
・経済:撤去・修復にかかる莫大な公費(税金)が必要になる
-
・社会:土地や不動産の価値低下、地域住民の健康被害リスク、行政や地域に対する不信感
これらの影響は、最終的には地域住民や私たちの生活に深刻な影響を及ぼします。日本の産業廃棄物最終処分場の残余年数は約20年しかありません。
一部のゴミは、正しく処理されればリサイクルにより再利用が可能ですが、不法投棄され放置されるとリサイクルされず、結果的に最終処分場を圧迫することになります。
実際に起きた産業廃棄物の不法投棄事例
実際に起きた不法投棄事例のなかでも、とくに有名なものは以下のとおりです。
-
・香川県の豊島で有害産業廃棄物を不法投棄
-
・兵庫県の町有地に産業廃棄物を放置
-
・京都府で解体がれきを無許可で埋め立て
ひとつずつ解説します。
観光開発会社による不適正処理、約91万トンの廃棄物が撤去された豊島事件
1970年代後半から約20年にわたり、香川県の豊島(てしま)で観光開発会社が廃棄物の処理を請け負いながら、許可範囲を超えて産業廃棄物を搬入・保管していました。結果として、約91万トンの廃棄物や汚染土壌が島内に不法に投棄され、土壌や地下水の汚染が深刻化しました。
長年にわたる住民の訴えを受け、2000年には香川県と住民団体との間で公害調停が成立。県が責任を持って撤去と無害化処理を行うこととなり、撤去・処理費だけで約727億円、跡地整備や地下水管理を含めた総事業費は2023年時点で約820億円にのぼりました。
豊島事件は、日本最大級の不法投棄問題として知られ、廃棄物処理の監督体制や事業者責任のあり方を見直す契機となった象徴的な事例です。
建設工事会社が町有地に廃棄物放置、2億円の賠償請求へ
兵庫県上郡町では採石場跡地の町有地を建設工事会社に契約付きで貸与していました。会社はその土地を建設廃材の仮置き場として使用していましたが、契約期限が切れた後も産業廃棄物を放置し続けていたのです。なかにはアスベストを含む廃材も混在しており、安全に撤去するには高額な費用が必要となりました。
自治体は、建設工事会社に対し撤去費や損害賠償として約2億円を請求する方針を示しています。なお、周辺環境については基準を上回る有害物質は検出されなかったものの、放置された廃棄物は地域の不安を招く要因となりました。
解体工事会社らが44トンを無許可埋立、経営者4人逮捕
京都府京都市では、民家の解体で発生した産業廃棄物を無許可で埋め立てたとして、建設土木工事会社の社長や解体工事会社の社長ら4人が逮捕されました。対象となったのは木造民家2棟分、約44トンものがれきです。
これらは、東高瀬川と宇治川の合流地点近く、建設土木会社社長が所有する土地に埋め立てられていました。
不法投棄に対する罰則と企業リスク
ここまで解説したように、不法投棄は主に費用軽減を目的に行われます。しかし、不法投棄には厳しい罰則が設けられており、企業の信用やブランドも大きく損なう行為です。
ここでは、産業廃棄物処理法における罰則と、企業が負う社会的リスクを詳しく解説します。
産業廃棄物処理法における罰則
不法投棄は産業廃棄物処理法で厳しく規制されており、個人・法人を問わず重い刑事罰や行政処分の対象となります。
主な罰則は以下のとおりです。
-
・無許可営業:5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
-
・不法投棄:5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)
-
・行政処分:許可の取り消しや事業停止命令など
罰則は、不法投棄を行った廃棄物処理業者だけでなく、依頼した排出事業者にも適用されるケースもあります。特に注意すべきは、排出事業者が委託した処理業者による不法投棄であっても、排出事業者自身が罰せられる可能性がある点です。そのため、依頼する側も正しい処理方法を実施している会社を選ばなければいけません。
企業が負う社会的リスク
不法投棄が発覚した企業は、法的な罰則に加えて、社会的な信用も失います。環境問題に対する世間の目が厳しい今、ブランドイメージや社会的信用を失うリスクは深刻です。
具体的には、以下のような問題が生じるでしょう。
-
・企業ブランドの大幅な失墜、取引先からの信頼喪失
-
・行政からの指導や監視強化、場合によっては取引停止
-
・原状回復費用の負担による経済的損失
-
・CSRやESG投資の観点からもマイナスイメージ
もしも、不法投棄により周辺住民への健康被害が出ていた場合、住民が訴訟し裁判にまで発展する可能性もあります。裁判費用や保証金額によっては、会社の存続すら危ぶまれるので、社会的信用を守るためにも、適正な廃棄物処理を行うことが不可欠です。
不法投棄を防ぐために排出事業者ができること
ここでは、不法投棄を防ぐために排出業者ができることとして、以下の3点を紹介します。
-
・適正処理業者を選定する
-
・マニフェスト制度を正しく運用する
-
・定期的なチェックと教育を行う
順番に見ていきましょう。
適正処理業者を選定する
不法投棄の多くは、処理を委託した業者が不正を行うことで発生しています。そのため、排出事業者にとって最も重要なのは「適正な処理業者を選ぶこと」です。
適正処理業者を選ぶ際は、以下のポイントを押さえましょう。
-
・優良産廃処理業者認定制度を活用し、信頼できる業者を選ぶ
-
・許可証の有効期限や処理範囲を確認する
-
・実績・処理施設の有無をチェックし、現場を見学する
また、処理料金が極端に安い業者には注意してください。産業廃棄物を正しく処理するためには一定の費用がかかるため、極端に安い処理料金ではまず受けられません。適正処理業者であれば、ある程度の処理料金を請求するのが一般的です。
マニフェスト制度を正しく運用する
マニフェスト制度は、排出された廃棄物が最終処分まで適正に処理されることを追跡できる仕組みです。正しく運用すれば、不正を防ぐ抑止力になります。
マニフェスト制度を活用する際のポイントは、以下のとおりです。
-
・マニフェストを確実に発行・回収し、記録を残す
-
・最終処分までトレーサビリティを確保する
-
・委託先が義務を怠っていないか定期的に確認する
マニフェストは法律上、排出事業者が発行することになっています。ただし、実務上は処理を委託した業者が代行してマニフェストを作成・印字するケースも多く見られます。
その場合でも、最終的な責任は排出事業者にあるため、内容を確認し、制度を正しく理解したうえで運用することが大切です。
マニフェストは紙媒体と電子媒体のどちらでも運用できます。最終的に排出事業者の手元に返ってくるため、保管しやすい方法を選択するとよいでしょう。
定期的なチェックと教育を行う
不法投棄は、委託先業者の不正だけでなく、排出事業者の従業員や下請け現場で発生することもあります。そのため、委託先任せにせず、自社内でのチェック体制と教育を徹底することが欠かせません。
産業廃棄物処理の必要性や排出事業者に課せられている責任、不法投棄により起こりうるリスクについて、定期的に教育しましょう。その上で、定期的なチェック・教育で効果的なものが以下のとおりです。
-
・委託先業者や処理記録の定期チェックを行う
-
・社内で産業廃棄物処理に関する教育を実施する
-
・CSR活動の一環として環境保全の取り組みを共有する
これにより、排出事業者の社員ひとり一人が、「不法投棄をしてはいけない」という意識が向上するでしょう。
まとめ
産業廃棄物の不法投棄は、法律違反にとどまらず、企業の信用や社会的評価を大きく損なう行為です。放置された廃棄物は環境や地域住民にも深刻な悪影響を及ぼし、撤去や修復にかかる莫大な費用は最終的に社会全体の負担となります。適正処理の徹底は企業責任であり、信頼を守る行動です。
排出事業者は、適正処理業者の選定やマニフェスト制度の活用、社内教育を通じて不正を防ぎましょう。なにより、「不法投棄をした産業廃棄物処理事業者と処理を依頼した排出事業者両方に責任が問われること」を理解してしてください。
このように、産業廃棄物の不法投棄を防ぐためには、正しい業者選びとマニフェスト管理が重要です。もし、業者選びや産業廃棄物の管理に困ってしまう場合は、環境のミカタへお気軽にご相談ください。スポット的に発生した処理にも、柔軟に対応いたします。