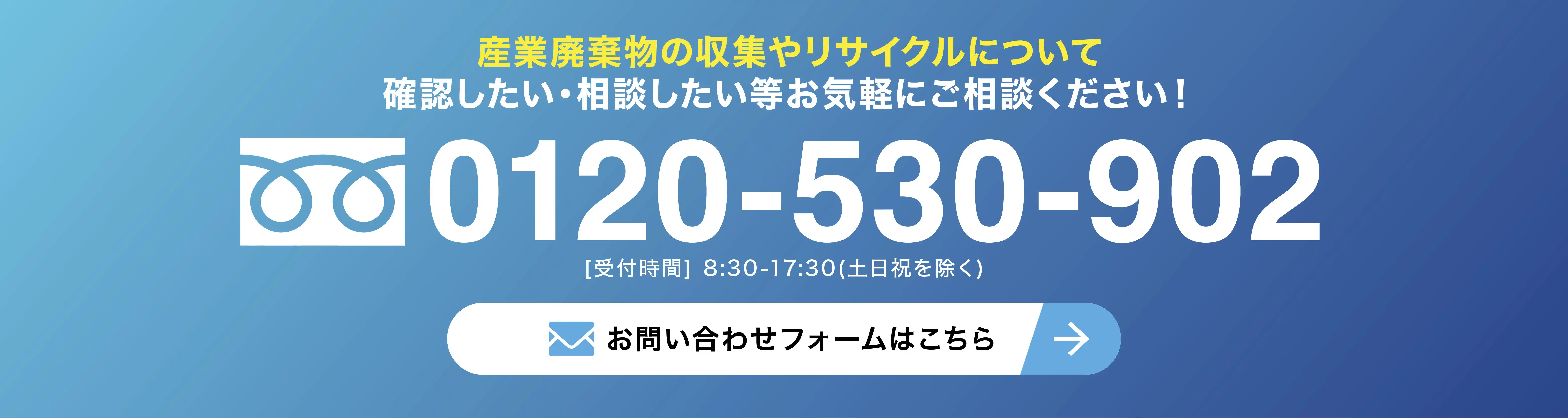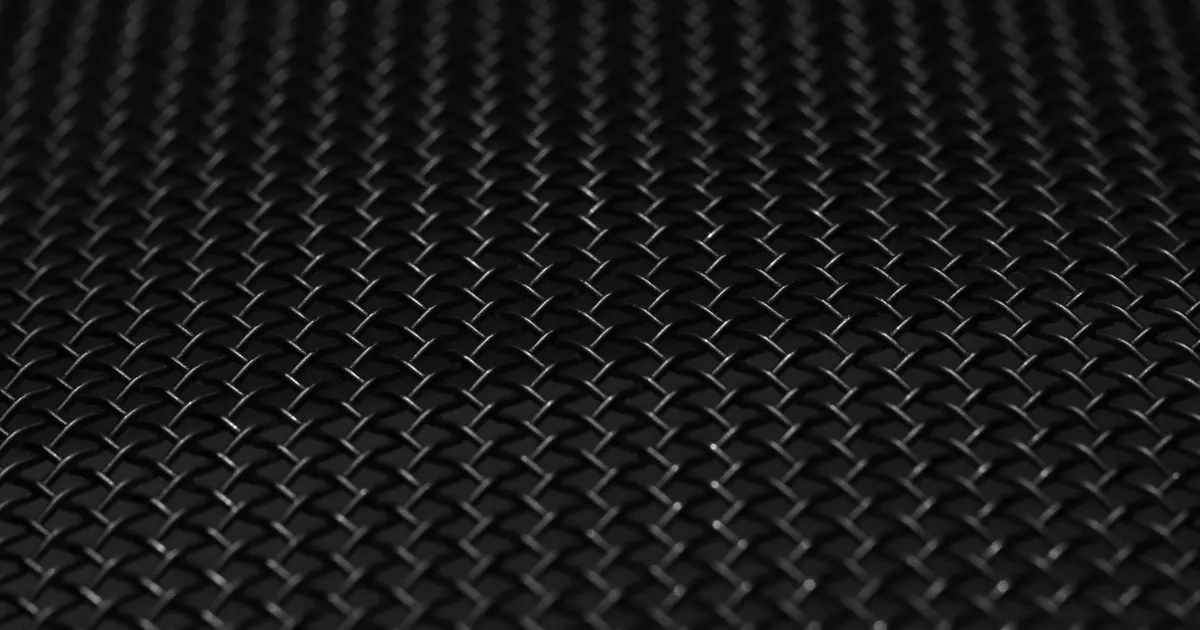
CFRP(炭素繊維強化プラスチック)のリサイクルとは、使用済み製品から炭素繊維と樹脂を分離して再利用する取り組みです。これによって、資源の有効活用と環境負荷の低減を目指します。しかし、CFRPのリサイクルは経済的・技術的な課題が大きく、十分に普及していないのが現状です。
本記事では、CFRPリサイクルの必要性や現状・課題、そして今後の展望について解説します。CFRPのリサイクルについて詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
CFRPリサイクルの現状
CFRPのリサイクルは世界的に見てもまだ十分に普及していません。経済産業省によると、2022年時点で世界における炭素繊維(CF)のリサイクル率は約6%に留まっています。
この背景には、CFRP特有の構造や性質に起因する問題が存在します。CFRPは炭素繊維(CF)と樹脂が強固に結びつくことにより高い強度を実現している複合素材です。しかし、その強固さゆえに、炭素繊維と樹脂の分離には多大なエネルギーを要します。この性質は、再資源化にかかるコストを増大させて、リサイクルの普及を妨げています。
また、リサイクルされたCFRPは再生炭素繊維(RCF)としての活用が期待されている一方、分離処理に伴う強度の低下が懸念される点も、普及が進まない要因のひとつです。
CFRPリサイクルの必要性
さまざまな分野で使われるCFRPは、今後も需要の拡大が見込まれています。しかし、化石資源が原料なため、長期的な資源枯渇や価格変動のリスクも指摘されています。
また、CFRPはシート状の中間材料から必要な部分だけを切り出して使うケースが多いです。そのため、製造工程で多くの端材や廃材が発生するという特徴もあります。
さらに、前述のようにCFRPのリサイクル率は著しく低く、その廃棄は埋立処理に依存している状況です。国内の最終処分場の残余面積は年々減少しており、このまま埋立処分に依存し続けると、処分場の逼迫がさらに進むことも懸念されています。
将来的な資源リスクや廃棄問題に対応しつつ、拡大する需要に応えるためにも、CFRPのリサイクル体制を含む資源循環の仕組みづくりが求められるでしょう。
CFRPリサイクルの技術
CFRPのリサイクル技術としては、以下が挙げられます。
-
・熱分解法
-
・化学分解法
-
・機械分解法
-
・マイクロ波による分離法
-
・電解硫酸法
-
・製鋼副資材への加工
技術ごとに異なる特徴やメリット・デメリットがあるため、用途や目的に応じて使い分けられています。
熱分解法
熱分解法は、CFRPを450℃以上の高温で加熱して、炭素繊維と樹脂を分離させる技術です。比較的簡単に分離できるのが利点となります。
一方で、炭素繊維の強度が低下する可能性があるほか、高温を要するのでエネルギーコストや環境負荷の面での懸念があります。
化学分解法
化学分解法は、CFRPに含まれる樹脂を化学薬品で溶解し、炭素繊維と分離させる技術です。この方法の強みは、炭素繊維の強度を保ったまま回収できる点です。
ただし、使う薬品の取り扱いや廃液処理には高度な管理が求められます。また、薬品による環境負荷やコスト面での課題も挙げられます。
機械分解法
機械分解法は、CFRPを物理的な手法で粉砕して、炭素繊維と樹脂を分離させる技術です。設備コストが比較的低い点がメリットとなっています。
ただし、炭素繊維が短く切断されるため、元のような高性能素材としての再利用は難しく、使用用途が限られてしまうのが課題です。
マイクロ波による分離法
マイクロ波を使った分離法では、炭素繊維がマイクロ波を吸収して内部発熱する特性を活かし、CFRPを内部から加熱して樹脂と分離します。外部加熱と異なり、繊維の品質を落とさず、効率的に炭素繊維を回収できる点が特徴です。
今後の普及が期待される、次世代リサイクル法の一つといえるでしょう。
電解硫酸法
電解硫酸法は、硫酸の電気分解により生成する強い酸化力を持つ物質(酸化性活性種)を利用し、CFRPの樹脂成分を分解して炭素繊維を取り出す方法です。回収された連続炭素繊維は、新品と同等の強度を保てます。
マイクロ波によるリサイクル法と同様に、今後の普及が期待されるリサイクル技術です。
製鋼副資材への加工

CFRPを含む処理困難物を利用し、製鋼副資材として生まれ変わらせるリサイクル技術も登場しています。株式会社大瀧商店が開発した技術では、CFRPを鉄粉とあわせて破砕・圧縮成形し、製鉄工程で使用される加炭材へ再資源化が可能です。
その後、電炉メーカーに供給し、鉄スクラップとともに電炉で溶解・製鉄されます。これにより、従来は埋立処理されていたCFRPを有効資源として循環させられるでしょう。
また、鉄鋼業界においても化石資源由来の材料使用量を抑制可能です。CO₂排出量の削減や資源の有効活用といった環境面での効果も期待されています。
静岡県を中心に廃棄物のリサイクル事業を展開している環境のミカタは、2026年に新工場「Earth Protection Center ZERO」の稼働を予定しています。大瀧商店との資本提携により、CFRPを含む複合材料を製鋼副資材として再資源化する取り組みを進めています。従来は難しかった処理困難物のリサイクルを、より幅広い角度から実現します。CFRPのリサイクルに興味のある方は、ぜひ一度ご相談ください。
CFRPリサイクルの今後の展望
CFRPは、環境負荷の低減を求められる分野でも注目を集めています。例えば、自動車にCFRPを使用すれば、軽量化により燃費が向上し、CO₂排出量の削減につながります。
カーボンニュートラル実現に向けた取り組みとともに、CFRPの需要は今後も増加していく見込みです。環境への影響を抑えながら増加する需要に対応するためにも、CFRPの再資源化はますます重要になっています。
環境負荷が少ないリサイクル技術や繊維の強度や長さを損なわずに回収する技術の開発のほか、製鋼副資材としての再資源化など、多様なリサイクルルートの確立が期待されています。
まとめ
CFRPは、優れた特性を持つ素材として幅広い分野で活用されている素材です。しかし、その構造や性質により、現状では十分にリサイクルが普及しているとはいえません。
とはいえ、資源の枯渇や廃棄物処理場の逼迫といった課題を解決するには、CFRPの資源循環システムの構築が不可欠です。
環境のミカタでは、大瀧商店との資本提携により、CFRPを製鋼副資材として再資源化する新たなリサイクルルートを確立しました。CFRPの処理にお困りの企業様は、ぜひ環境のミカタにご相談ください。